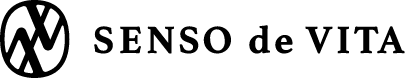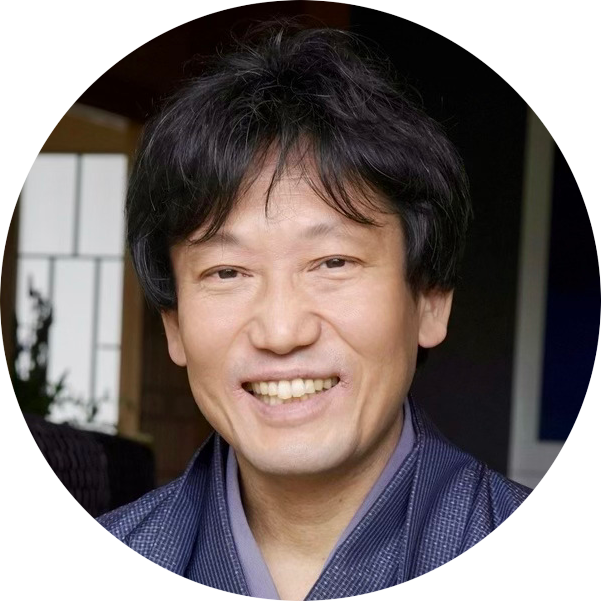先日 朝から所用を済ませ 急ぎ特急で高野山へ。
せっかく祭りの日に行ったのだが 私が着いた時刻にはちょうど終わった頃だった。。
少し残念だが 祭りの後の雰囲気を味わうのも悪くない。
高野山に着くとすぐに奥の院へ。 一の橋から参道を行く。
少し歩くと 司馬遼太郎の石碑が。
「・・出発点には・・大門がそびえている。 大門のむこうは天である。
・・大門からそのような虚空を眺めていると この宗教都市がじつは現実のものではなく
空に架けた幻影ではないかとさえ思えてくる。
まことに、高野山は日本国のさまざまな都鄙のなかで 唯一ともいえる異域ではないか。」
読んでいるとなにやらそんな気分になってくる。いい感じだ。
明日は高野山正規の出発点、 大門から見学しようと思う。

薩摩藩主 島津義弘・忠恒父子が 慶長の役(1599年 朝鮮出兵)における
敵見方の戦死者の霊を供養するために建てたもので
日本武士道の博愛精神の発露として知られているらしい。
和歌山県指定文化財。

太平洋戦争 北ボルネオ島(マレーシア)で戦死した両軍の将兵 並びに
現地住民の総霊を弔っている。
敵味方、現地の方々を弔ってるのが日本らしくていいなと思う。
昔の精神は今も受け継がれているようだ。
ひときわ大きい異質な供養塔があったので近づいてみると
太平洋戦争 ビルマ方面において亡くなった18万余の方々を慰霊する
ために25年の歳月を経て建立されたビルマのパコダ形式の納骨塔であった。
何度も遺骨収集に参加され 合祀されたらしい。
少し脇にそれたところに織田信長の墓がひっそりと佇んでいる。
なぜか隣には明智光秀の与力大名 大和の筒井順慶の墓があった。
他家に比べるとかなり小さいのがとても不思議。
大東亜戦争で亡くなられた英霊を祀られた英霊殿。
大阪の一私人が 昭和52年に建立されたらしい。
こういうのが本当の文化的な町人の姿だと思う。
国に頼るのではなく 自費で。
英霊殿のそばに建てられた碑。
「 敷島の 大和心を 人問わば 朝日ににほふ 山桜花 」
私の好きな本居宣長の句があった。 ちょっと感動した。
御廟橋を超えると大師御廟の霊域へ。
左手に宮内庁管轄の土地があった。
お参りを済ませ 帰りは中の橋案内所の方へ。
行きとは一転 近代的なお墓が並び 南海電車や福助、シャープなど 有名な企業から
一私人の墓まで、 形も 宣伝活動を兼ねているのか ロケットやら福助人形や白アリの墓など
多彩であったが なにか軽さを感じた。
バスに乗って 宿泊先の宿坊「一乗院」へ。
17時までにチェックインするよう 言われている。